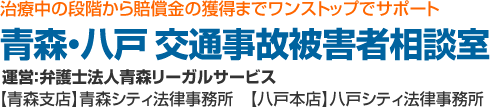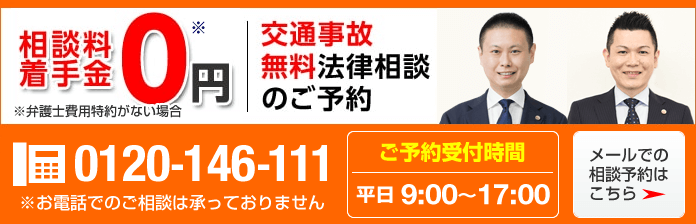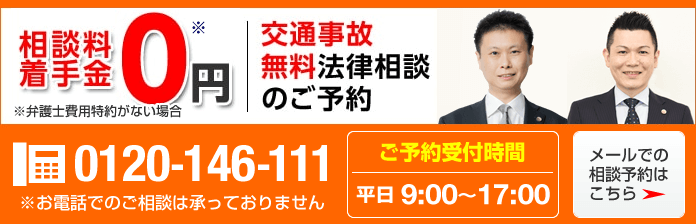2023年5月20日、日本交通法学会の定期総会・個別報告・シンポジウムが東京で開催され、弁護士・木村哲也が講演「若年未就労の障害者の逸失利益算定方法について」を受講してきました。
講演では、「若年未就労の障害者が、不法行為により命を奪われ、あるいは後遺障害により労働能力を喪失した場合に、逸失利益をどのように計算するべきか?」という論点について、近時の裁判例の紹介を交えた解説がありました。
【裁判例1】
事故時17歳の全盲の若年未就労者が労働能力を全喪失した事案ついて、第一審(山口地方裁判所下関支部令和2年9月15日判決)は全労働者平均賃金の7割、第二審(広島高等裁判所令和3年9月10日判決)は全労働者平均賃金の8割に相当する額を基礎収入と認定しました(確定)。
【裁判例2】
事故時11歳の難聴の若年未就労者が死亡した事案について、第一審(大阪地方裁判所令和5年2月27日判決)は全労働者平均賃金の8割5分に相当する額を基礎収入と認定しました(控訴予定)。
【裁判例3】
自閉スペクトラム症を有する知的障害者である15歳の若年未就労者が死亡した事案について、第一審(東京地方裁判所平成31年3月22日判決)は19歳までの全労働者平均賃金に相当する額を基礎収入と認定しました(確定)。
これらの裁判例では、障害者法制の整備等による社会の変化、テクノロジーの発達による就労支援機器の充実等を踏まえ、被害者が潜在的な稼働能力を発揮して健常者と同様の賃金条件で就労する可能性などを肯定する一方で、結論として障害者でない者と同額の逸失利益の算定を否定しています。
その理由として、①障害者と障害者でない者との間に就労格差や賃金格差が存在すること、②被害者が潜在的には障害者でない者と同等の稼働能力を有するとしても、就労可能年数のいかなる時点で、潜在的な稼働能力を発揮して健常者と同等の賃金条件で就労することができるか不明であること、③労災保険法施行規則や自賠法施行規則においてその程度に応じて後遺障害の等級が定められ、労働能力喪失率が定められていることからすれば、障害が労働能力を制限し得る事実であることは否定できないこと、などが挙げられています。
しかし、①就労格差・賃金格差の存在については、現在および過去の障害者に対する差別の結果であると言い得るところ、そのような差別を反映した現在の労働市場における障害者の賃金水準を参照することは不適切である、という反論があります。
また、②被害者の労働能力の立証については、障害者と障害者でない者との立証責任の格差が問題視され得るでしょう。
すなわち、現行の実務では、障害者でない若年の未就労者について、具体的な能力証明を要求することなく、賃金統計の平均賃金を基礎収入として、逸失利益を計算することを原則としています。
その一方で若年未就労の障害者について労働能力の立証を厳格に要求することは、このような現行の実務と整合するのか、という問題です。
そして、③障害による労働能力の制限については、現在の日本社会は、障害者がその障害を理由として、当然に労働能力を制限される社会ではない、と言うことができます。
しかし、たとえ障害者法制に基づく合理的配慮が提供され、最新の就労支援機器が利用可能であったとしても、すべての障害者が就労可能期間を通じて障害のない者と同じように仕事をし、労働の賃金を得られるわけではありません。
だからこそ、障害者の逸失利益を計算する際には、「障害者」を一括りにするのではなく、個々の障害者の有する稼働能力の有無、程度を具体的に検討したうえで、一般就労の可能性の有無、程度を判断することが求められる、と考えられます。
このように、若年未就労の障害者の逸失利益算定方法には、複雑な問題があります。
この論点については、今後も裁判例や議論の行方を注視していく必要があるでしょう。
(弁護士・木村哲也)