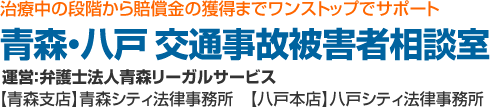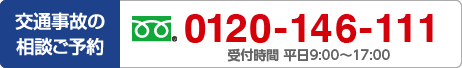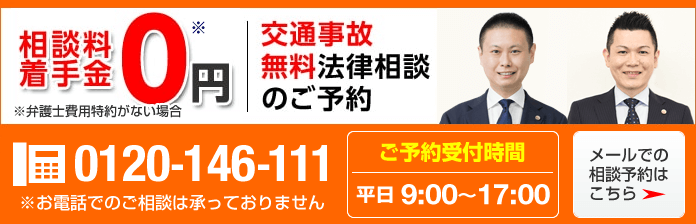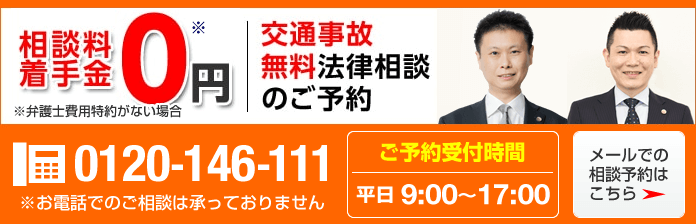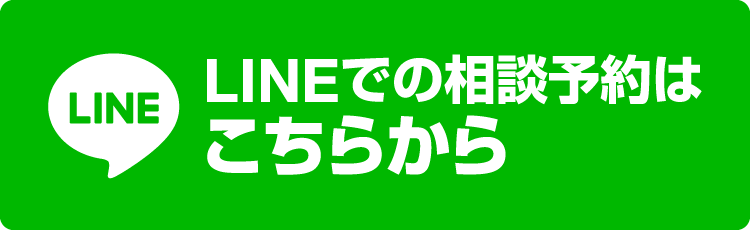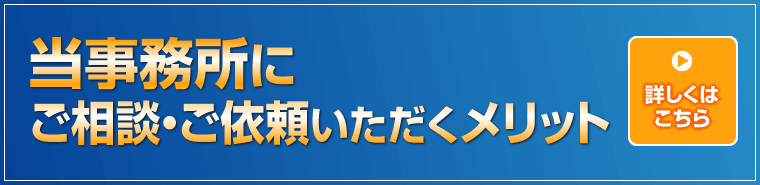1 交通事故における慰謝料とは?

交通事故における慰謝料とは、被害者が受けた精神的損害(苦痛)に対する金銭での補償のことをいいます。
慰謝料(の機能)は、被害者が受けた精神的ダメージを、金銭を受領することによる満足感・幸福感により和らげ、精神の均衡を回復するもの、と考えられています。
2 交通事故における慰謝料の種類
交通事故における慰謝料には、次に解説するとおり、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3つの種類があります。
(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故による怪我で病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことです。
交通事故の怪我による精神的損害としては、次のようなことが考えられています。
〇怪我を負ったことによる肉体的ダメージ
〇入院や通院により時間が取られて行動の自由が制限されたことによる精神的ダメージ
〇肉体的ダメージや治療の必要上行動の制限を受けるため、活動が十分にできないことによる不利益
こうした精神的損害の内容や程度は、その事故ごとのケースバイケースであり、個別に正確な金銭評価をすることは困難です。
そのため、後に述べるとおり、実務では原則として入通院の期間を基準に、入通院慰謝料(傷害慰謝料)の額が算定されます。
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我で後遺障害が生じた場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。
これ以上治療を続けても改善が期待できない場合に、症状固定となり、後に残る障害が後遺障害となります。
これ以上治療を続けても改善が期待できないことにより、将来にわたって残り続ける苦痛、外見の悪さ、生活への影響などに対する金銭での補償として考えられています。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて標準額があります。
後遺障害慰謝料についてはこちらもご覧ください
●後遺障害慰謝料とは?
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が亡くなられた場合の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。
被害者自身の慰謝料については、本人が亡くなっている以上、被害者の相続人が加害者に対して賠償請求することになります。
死亡慰謝料の金額については、被害者の属性に応じた一応の標準額があります。
死亡慰謝料についてはこちらもご覧ください
●死亡慰謝料とは?
3 交通事故における慰謝料の計算方法
交通事故における慰謝料の計算方法について、このページのテーマである交通事故における通院日数と慰謝料の関係の解説として、上記のうち、(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法を解説します。
以下では、入通院慰謝料(傷害慰謝料)を単に「慰謝料」と記載します。
(1)慰謝料の金額はどうやって決まるのか
慰謝料が精神的苦痛に対する補償であるとすると、同じような交通事故の被害を被っても、それによって感じる精神的苦痛は人によって様々であるから、同じような被害であっても、慰謝料の額は被害者によってバラバラになるはずともいえます。
しかし、それでは不公平であるし、また、個別に正確な金銭評価をすることは困難です。
そこで、実務においては、慰謝料の額は入通院の期間に応じて基準化されています。
他覚症状のないむちうち症や軽度の打撲・挫傷については、被害者の方の気質的なものや年齢的なものによって、入通院の期間が長引くことがあるため、傷害慰謝料の額が他の傷害の7割程度として算定されます。
(2)交通事故の慰謝料に関する3つの基準
慰謝料の算定方法には、以下の3つの基準があります。
①自賠責保険の基準
②任意保険の基準
③裁判の基準
これはあまり知られていない事実なのですが、保険会社は最も低い自賠責保険の基準で示談金の提案をしてくるケースがあります。
適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準については十分に理解をしておくことが必要です。
ここでは各基準について、詳しく説明していきます。
①自賠責保険の基準
自賠責保険はあくまで交通事故被害者の最低補償を目的として作られた保険であるため、賠償額を計算する際に自賠責保険の基準を使うと、3つの基準の中で最も低額の賠償金額になります。
自賠責基準の慰謝料の計算方法は、
次の2つのうち、低い方の金額となります。
〇4300円×治療期間
〇4300円×{入院日数+(実通院日数×2)}
例えば、治療期間6か月(180日)のうち、実際に通院したのが50日の場合(入院なし)、〇4300円×180日=77万4000円、〇4300円×{0日+(50日×2)}=43万円という計算結果になり、低い方の金額である43万円が採用されます。
なお、実際に治療期間が6か月間に及ぶ場合、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料の合計が自賠責保険の上限である120万円を超えるケースが多く、その場合は120万円に達するまでの慰謝料が支払われるに過ぎません。
②任意保険の基準
任意保険の基準とは、加害者が加入している対人賠償責任保険の保険会社内部の基準のことです。
任意保険の基準で賠償金額を算出すると、一般的に自賠責保険よりも高いですが、裁判の基準よりも低額になります。
なお、保険会社が任意保険の基準で算定した金額を常に提示してくるわけではなく、自賠責の基準とほとんど変わらない金額を提示する保険会社が多いのが実情です。
③裁判の基準
裁判の基準とは、裁判所と弁護士会が過去の判例を踏まえて作成した基準のことです。
裁判の基準で賠償金額を算出した場合、ほとんどの場合において、自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した賠償金額よりもずっと高額になります。
そのため、交通事故の被害者が慰謝料の相場や算定方法を知ろうとする場合、この裁判の基準を十分に理解しておくことが重要です。
自賠責保険の基準 < 任意保険の基準 < 裁判の基準
裁判所は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(いわゆる赤い本)に従って、迅速かつ公平な観点から基準化された慰謝料を計算するケースが多いです。
また、裁判の基準の慰謝料を算定する場合、以下のようにケガの内容に応じて二つの表を使い分けます。
原則として入通院期間を基礎として下記の別表Ⅰによります(通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります)。
他覚症状のないむち打ち症や軽度の打撲・挫傷の事案では、下記の別表Ⅱによります(通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります)。
別表Ⅰ(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
別表Ⅱ(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
たとえば、骨折で6か月通院したという場合には、別表Ⅰで、116万円の慰謝料となります。
また、むちうちで6か月通院したという場合には、別表Ⅱで、89万円の慰謝料となります。
このように、むちうちであった場合でも、弁護士基準で計算した慰謝料は自賠責基準や任意保険基準よりも高額になることが多いです。
(3)骨折の場合の通院日数と慰謝料の関係
【1か月入院、6か月通院の場合】
骨折で1か月入院(30日)、6か月通院(180日、実通院日数60日)だった場合のそれぞれの基準で算出される慰謝料は以下のとおりです。
〇自賠責保険の基準 - ※
〇任意保険の基準 85万円程度
〇裁判の基準 149万円
※骨折で1か月入院、6か月通院の場合、多くのケースで自賠責基準の上限120万円に達しますので、120万円の上限額に達するまでの慰謝料がもらえるに過ぎません。
【2か月入院、8か月通院の場合】
骨折で2か月入院(60日)、8か月通院(240日、実通院日数100日)だった場合のそれぞれの基準で算出される慰謝料は以下のとおりです。
〇自賠責保険の基準 - ※上記同様
〇任意保険の基準 121万円
〇裁判の基準 203万円
(4)むちうちの場合の通院日数と慰謝料の関係
【1か月通院の場合】
むちうちで1か月間(30日)に、週3回程度のペースで合計12回整形外科に通院した場合、それぞれの基準で算出される慰謝料は以下の通りです。
〇自賠責保険の基準 10万3200円
〇任意保険の基準 13万円程度(旧任意保険基準の表による。以下同じ)
〇裁判の基準 19万円
【3か月通院の場合】
むちうちで3か月間(90日)に、週3回程度のペースで合計36回整形外科に通院した場合、それぞれの基準で算出される慰謝料は以下の通りです。
〇自賠責保険の基準 30万9600円
〇任意保険の基準 38万円程度
〇裁判の基準 53万円
【6か月通院の場合】
むちうちで6か月間(180日)に、週3回程度のペースで合計72回整形外科に通院した場合、それぞれの基準で算出される慰謝料は以下の通りです。
〇自賠責保険の基準 61万9200円(ただし限度額あり)
〇任意保険の基準 65万円程度
〇裁判の基準 89万円
(5)通院日数が少ないと慰謝料にどう影響する?
裁判の基準でも、通院日数が少ない場合、慰謝料が低額になる可能性があります。
通院期間に対し実際に通院した日数があまりにも少ないケースでは、次のように修正した計算として「みなし通院期間」が使われることがあります。
〇別表Ⅰの場合:実通院日数×3.5
〇別表Ⅱの場合:実通院日数×3
別表Ⅰでは、「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合」にはみなし通院期間を適用することがあるとしています。
「長期」とは、概ね1年以上と考えられています。
「不規則」とは、通院頻度が通常の治療経過を反映しておらず、治療の必要性に疑問がもたれる場合などを想定したものと考えらえています。
そのため、骨折で自然治癒(骨癒合)を待つために通院日数が少ない場合、相手方保険会社から「みなし通院期間」を主張されることがありますが、このような主張に対しては、医師の治療方針に従った自宅療養は治療のため必要なものですので、通院期間として計算するよう反論していくべきでしょう。
別表Ⅱでは、別表Ⅰのような留保なし、「慰謝料算定の通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする」として修正した計算が原則とされています。
別表Ⅱでみなし通院期間が適用されてしまうと、慰謝料の金額は次のように減額されてしまいます。
(例)むちうちで6か月通院の場合
〇適切な通院日数であれば慰謝料は、89万円
〇通院期間6か月に対し、週1回程度の通院で、実通院日数が30日しかなく、みなし通院期間」90日(30日×3)」となった場合、慰謝料は、53万円
上記の例では、裁判の基準の場合でも、通院日数によっては慰謝料に36万円もの差が生まれてしまうことがわかります。
みなし通院期間の適用を受けないペースとしては、平均して月10日以上、3日に1回のペースでの通院となります。
もちろん、慰謝料のために必要のない通院をすることはあってはならないことは当然です。
怪我の種類や症状の重さ、治療経過等によって適切な通院日数は変わってくるので、医師と相談したうえで通院することが大切です。
4 交通事故に関するお悩みは当事務所にご相談ください
通院日数と慰謝料の関係についてこれまで解説してきたように、通院日数が極端に少ない場合は、入通院慰謝料が低額になってしまう可能性もあります。
しかし、「仕事が忙しくて通院できない」、「家事や育児が忙しくて通院できない」など様々なお悩みをお持ちでしょう。
通院日数と慰謝料の関係については、正しい知識がないまま交渉を進めると不利な状況に陥ってしまう場合もあります。
裁判の基準で計算することはもちろん、通院日数が少ない場合に「みなし通院期間」の主張をされた場合でも適切に反論して、相手方保険会社と交渉していくことで当初の提示額より増額する可能性が高まります。
交通事故における通院日数や慰謝料について少しでも不安がある場合は、一度当事務所にご相談ください。
(弁護士・山口龍介)